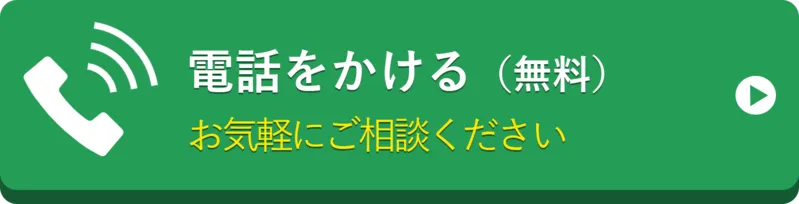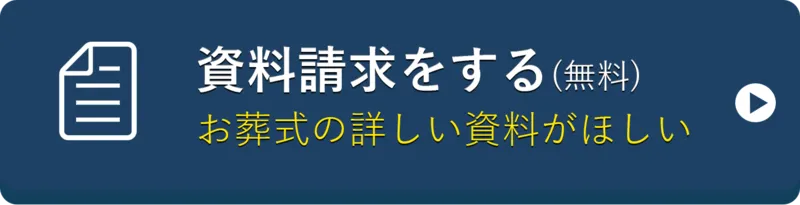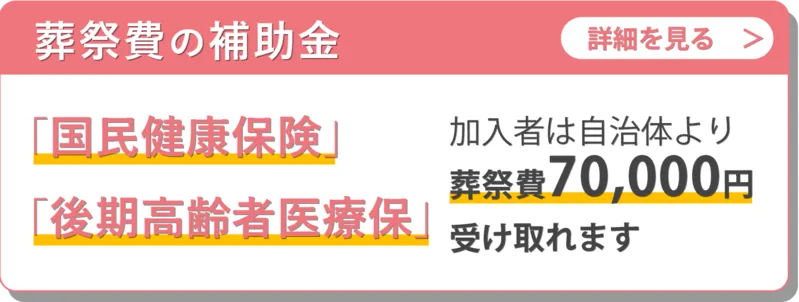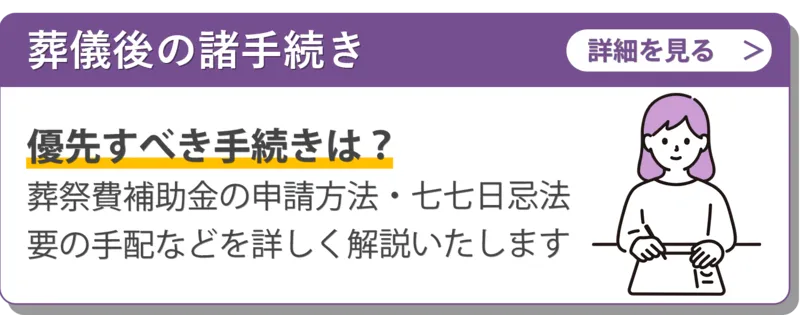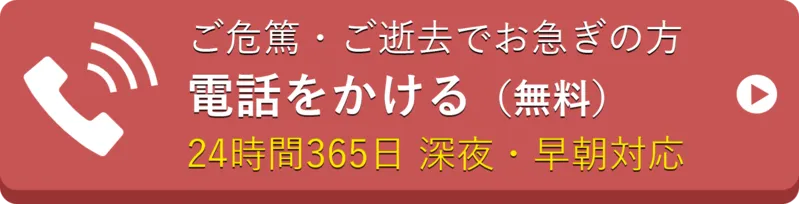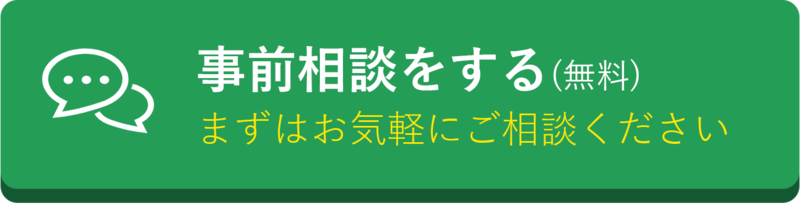喪主(もしゅ)とは、ご遺族の代表であり、葬儀社との打合せ・参列者や僧侶への応対など、参列者に対応するご葬儀の責任者となります。はじめての喪主として何をすべきか分からず悩んでしまうのは当然のことです。喪主としてはじめて葬儀を執り行う立場になった時に知っておくべきことを分かりやすくご説明いたします。
1. 誰が喪主になるか
明確な決まりはありません。喪主を務める人に「法的な順番・性別・年齢制限」はなく、一般的には故人の配偶者(夫または妻)が喪主を務めます。喪主が高齢の場合には名前だけ喪主として使用し、実際の葬儀の責任者(施主)としては長男・長女などが行うケースもあります。
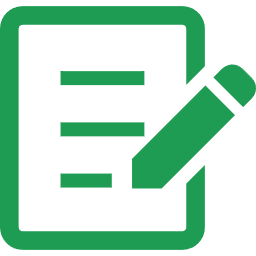 MEMO
MEMO
【 喪主の順番 】
①配偶者(夫または妻) ⇒ ②長男 ⇒ ③次男 ⇒ ④それ以降の直系男子 ⇒ ⑤長女⑥次女 ⇒ ⑦それ以降の直系女子 ⇒ ⑧故人の両親 ⇒ ⑨故人の兄弟姉妹…
 喪主と施主って違うの?
喪主と施主って違うの?
施主(せしゅ)とは、葬儀費用を負担・運営する人で、喪主のサポート役です。昔は夫が死亡した場合、家を継ぐ長男が喪主を務め、配偶者(妻)が施主というパターンが多く見られました。
現在では喪主と施主を分けず「喪主=施主」と両方を兼任することが一般的です。
2. 葬儀社との打ち合わせ
はじめてに葬儀を執り行う場所と葬儀の日程を決めます。その後、葬儀の形式(葬儀プラン)や会葬者に対するおもてなし(料理・返礼品)などについても話し合い取り決めます。葬儀社と事前相談をして予めご希望を伝えておくと、急なご逝去の場合でも打ち合わせがスムーズに進みます。
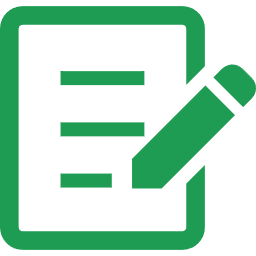 MEMO
MEMO
【 打ち合わせに必要なもの 】
- 死亡診断書と届出人の印鑑
葬儀の打ち合わせの際に、死亡診断書の記入や提出の際に届出人の印鑑が必要となります。印鑑はシャチハタではなく、朱肉を使って捺印するタイプの印鑑を使用します。 - 遺影写真の原板
遺影写真は、故人を偲ぶものとしていつまでも残るものです。故人さまの人柄が分かるような写真を選びましょう。カメラ目線でピントが合った写真であり、遺影写真として写真を引き伸ばすため解像度が高いものを選択いただけると良いでしょう。
【 葬儀社と打ち合わせの例文 】
「家族と近親者のみのお葬式で、家族は〇人、親戚は〇人、友人が数人来てくれそうです。お坊さんは○○寺さんで、宗派は○○宗です。式場は、近くを希望します。」
このように、希望式場やプラン、どんなお葬式にしたいか、簡単に希望をお知らせください。
 死亡届の提出場所について
死亡届の提出場所について
死亡届の提出は3か所の場所からお選びいただけます。①届出人の住所 ② 故人の本籍地 ③死亡した所 となります。葬儀後の諸手続きを考えると一般的には届出人(喪主)住所の自治体に提出することをおすすめします。
3. 菩提寺がある方は寺院へご連絡
故人さまがご逝去されたことを寺院にお知らせします。直葬(火葬のみ)や1日葬(告別式のみ)をご希望の場合は、菩提寺の了承を得る必要があります。近年では少人数で行う家族葬を選択する方がが多いため、直葬や1日葬も増えておりますがご理解いただけない場合は、通常の葬儀(通夜・告別式)2日葬を行う必要があります。
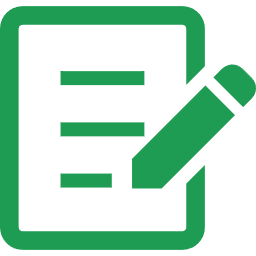 MEMO
MEMO
【 寺院との打ち合わせ内容 】
- 葬儀の形式、葬儀場
希望する葬儀の内容や式場・火葬場についてご相談します。 - 戒名(法名)
故人さまの命日、続柄、お名前、年齢や故人の人柄や職業、達成してきた業績などを伝えることでふさわしい戒名を授けてくださいます。 - お布施
一般的に、お布施はお気持ちでという言葉を耳にしますが、寺院によりお布施は異なります。「不慣れなことなのであらかじめ失礼のないように、お伺いしてもよろしいでしょうか」と、お布施をご確認してみるのも良いでしょう。 - 送迎の有無
式場まで送迎を希望する寺院もあります。寺院にご確認をしておくと良いでしょう。送迎が難しい場合には葬儀社にハイヤーまたはタクシーの手配をお願いする方法もあります。 - 食事の同席
通夜・告別式でお食事をする際、寺院にも同席いただけるかご確認しましょう。同席できない場合は、折詰または御膳料をご用意するとより丁寧です。
【 菩提寺へご連絡する例文 】
お世話になっております。○○の息子○○です。先ほど、父○○が亡くなりました。つきましては、ご住職様に葬儀のお勤めをお願いしたくご連絡いたしました。葬儀社と打ち合わせをしておりまして日程はお通夜◯月◯日〇時から、告別式は翌日〇時からと考えておりますがご住職様のご都合はいかがでしょうか?
 遠方の寺院でもご連絡は必須
遠方の寺院でもご連絡は必須
菩提寺が遠方(他府県)の場合でも、後々のトラブルを避けるためにも必ずご一報していただくことをおすすめします。
4. 親族・会社へご連絡
故人様がご逝去されたことをご親族さま、会社にお知らせします。訃報のご連絡が済み参列人数、供花について確認できしだい葬儀社へすみやかにお知らせください。訃報のお知らせをする際にお伝えする項目、例文をご紹介します。
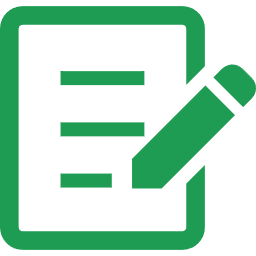 MEMO
MEMO
【 親族・会社へ訃報のお知らせと共にご確認すること 】
- ご参列人数のご確認
- 供花の申し出のご確認(札名もご確認)
「個人名」「連名」または「兄弟一同」「孫一同」などと共同で送る場合もあります。 - 供花の並べ方
喪主⇒親近者・親族⇒友人・知人⇒関係者という順で関係の深い順に並べます。
【 親族へ訃報を伝える際の例文 】
〇〇の長男の○○です。以前より入院していた父の○○が、〇月〇日の早朝に息を引き取りました。生前は大変お世話になりました。
葬儀の日程ですが、〇〇斎場で、お通夜は〇月〇日〇時から、告別式は○月〇日〇時から、〇〇式(宗教形式)で執り行う予定です。
ご会葬いただけますでしょうか?(人数確認)
ありがとうございます。何かあれば私の携帯にご連絡ください。連絡先は○○○-○○○○-○○○○です。
【 会社へ訃報を伝える例文 】
〇〇部△△課の□□□です。実は今朝、私の父が亡くなりましたのでご連絡させていただきました。私が喪主を務めますので、〇月〇日から〇日間の間、お休みをいただきたいのですがよろしいでしょうか。通夜や告別式の日時につきましては、決まり次第ご連絡いたします。お忙しいところ、何かとご面倒をおかけしますがよろしくお願い申し上げます。
【 家族葬で会社へ訃報を伝える例文 】
〇〇部△△課の□□□です。実は今朝、私の父が亡くなりましたのでご連絡させていただきました。〇月〇日から〇日間の間、お休みをいただきたいのですがよろしいでしょうか。通夜や告別式の日時につきましては、決まり次第ご連絡いたします。葬儀につきましては父の生前からの希望で、近親者のみで執り行なう予定です。お忙しいところ、何かとご面倒をおかけしますがよろしくお願い申し上げます。
※ご厚志を辞退する場合、こちらの文面を追加してください
ご厚志につきましても、大変失礼ながら辞退させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
家族葬の場合、厚志(弔電、供花、香典など)や弔問を辞退することが多い傾向です。辞退の意向であれば、会社側が対応に迷うことのないよう配慮し、その旨をはっきりと伝えるようにしましょう。
 注意
注意
弔問を辞退する場合、葬儀の会場や日時などの情報は社内に公開しないよう依頼します。事務手続き上必要となる情報以外にはそもそも伝える必要がありません。
5. 遺影写真の決定
遺影写真は、故人を偲ぶものとしていつまでも残るものです。“故人様のイメージ(雰囲気)が出ているお写真” や “ご家族が良いと思われるお写真” を選ばれることで素敵な遺影写真になります。判断に迷われた場合は、数枚ご用意ください。
- 「写真原板」「デジタルデータ」どちらからでも作成可能です。スマートフォンで撮影した写真をLINEで送信しますと画質が下がりますのでご注意ください。
- 最低限、運転免許証・証明写真くらいの大きさでお顔が映っている。画像が小さい場合、引き伸ばす工程(原板の20~40倍)で画像が粗くなります。
 ポイント
ポイント
- カメラ目線でピントが合った写真
- その人らしい服装の方が、故人さまを思い起こすきっかけにもなります
6. 喪主の挨拶
喪主の挨拶は、ほとんどの方が未経験で緊張される方も多いと思います。当日までに挨拶の内容を紙に書いておくのも良いと思います。近年では一般参列者がいない家族葬や直葬(火葬式)が増えており、喪主様の挨拶を省略する場合もあります。
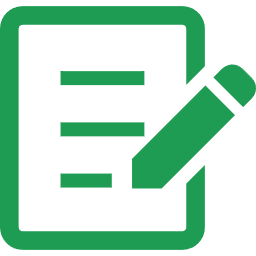 MEMO
MEMO
【 喪主の挨拶を行うタイミングは基本的に合計4回 】
- 通夜式終了後
- 通夜振る舞い
- 告別式終了後(出棺前)
- 精進落とし
【 ご挨拶のポイント】
「家族での思い出」や「普段、照れて言えなかった感謝の気持ち」など、難しく堅苦しく考えずに、“自分なりの言葉”で素直に故人と参列者への感謝の気持ちを述べることが最も大切です。ただ、不幸を繰り返さない意味で、「重ね言葉」は避けた方が良いとされていますので注意しましょう。
【 通夜式終了の挨拶 例文 】
長男の○○と申します。親族を代表いたしまして、皆様に一言ご挨拶を申しあげます。本日は、ご多用のところ(またお足もとの悪い中)、亡き父○○の通夜にご弔問くださり誠にありがとうございます。故人が生前たまわりましたご厚誼(こうぎ)と、ご厚情(こうじょう)に心より感謝申し上げます。親しくお付き合いいただいた皆様においでいただきまして、父も喜んでいる事と思います。本日は、誠にありがとうございました。
【 通夜式振る舞いの挨拶 例文 】
本日はありがとうございました。お陰様で、滞りなく通夜を終えることができました。お話は尽きませんが、遠方よりお越しの方もいらっしゃると思いますので、このあたりでお開きにさせて頂きたいと思います。なお、明日の告別式は○○時からとなっております。お時間がございましたら、お見送りに来て頂ければと思います。本日は、遅くまで本当にありがとうございました。
【 告別式終了、出棺の挨拶 例文 】
長男の○○と申します。親族を代表しまして皆様に一言ご挨拶を申し上げます。本日は、ご多用中にもかかわらず、ご会葬・ご焼香を賜りありがとうございました。
おかげをもちまして昨日の通夜、本日の葬儀・告別式を滞りなく執り行うことができました。最後までお見送り頂きまして父も喜んでいる事と思います。
故人のエピソード例に続く↓↓
父は、口数が少なく真面目で仕事一筋でした。家族を支え働き者だった父は、定年を機に山歩きにチャレンジ。目を輝かせながら語ってくれた谷川岳の景色。4年前に私や孫たちを尾瀬に連れて行き、自然の魅力に親しませてくれました。
しかし、その直後に闘病生活が始まったため、思うように山歩きもできなくなり、どんなに残念だったかと思います。我慢強い父は、入院中に愚痴をこぼすことは一度もありませんでした。
父は、真面目にコツコツと力強く人生を生き抜きました。私たちも父のように強く生きて行こうと思います。
なお、生前寄せられました皆様のご厚情(こうじょう)に対し、心より御礼申し上げます。残されました私ども家族に対しまして、今後とも、亡き父同様、ご指導ご厚誼(こうぎ)を賜りますようお願い申し上げます。
簡単ではございますが、遺族を代表しましてお礼の挨拶とさせていただきます。本日は、誠にありがとうございました。
【 精進落としの挨拶 例文 】
昨日から今日まで、長時間に渡りありがとうございました。皆様のお力添えをいただき、滞りなく葬儀を終えることができました。家族を代表しましてお礼申し上げます。
皆様、さぞお疲れのことと思います。誠にささやかではございますが、皆様への感謝と慰労を兼ねまして席をご用意いたしました。故人の思い出などをお聞かせいただきながら、ごゆっくりとお召し上がりいただきたいと存じます。本日はありがとうございました。
7. まとめ
葬儀が終わって一息つきたいところですが、喪主さまにとって未だやらなければならないことがあります。初めてのことで戸惑われることも多いと思いますが、どのようなことをやらなくてはいけないのかを知っておくだけでも、少しは気持ちが楽になるのではないでしょうか。

葬儀後の諸手続き、四十九日法要・納骨の手配、お香典返しなどやる事が多く、目まぐるしい日々が続きます。これらをどうすすめていくべきかのポイントは、自身でできることとプロに任せることのバランスが大切です。お一人で悩まずに仏事アドバイザーに相談してみませんか?「メモリアルプランナーみはし」は、すべての仏事相談を一箇所の窓口に集約しており、お客さまが相談しやすい環境づくりに日々取り組んでいます。親切、丁寧な対応を心掛けております。些細なことでもお気軽にご相談ください。
\気になる疑問をLINEで聞いてすぐ解決/
LINEからのお問い合わせはこちら
メモリアルプランナーみはし
荒川区で創業25年地域密着の葬儀社です
メモリアルプランナーみはし
荒川区で創業25年地域密着の葬儀社です
メモリアルプランナーみはしは人生のエンディングに携わる葬祭事業を展開しております。お客様が相談しやすい環境づくりとして東京都荒川区・埼玉県川口市にショールームを完備しており、終活相談やご葬儀の事前相談など無料でご案内しております。
店内には仏壇仏具・手元供養品・線香ローソクの他、墓石見本なども展示しており、お客様のお悩みに寄り添い、商品選びなどのお手伝いもしています。
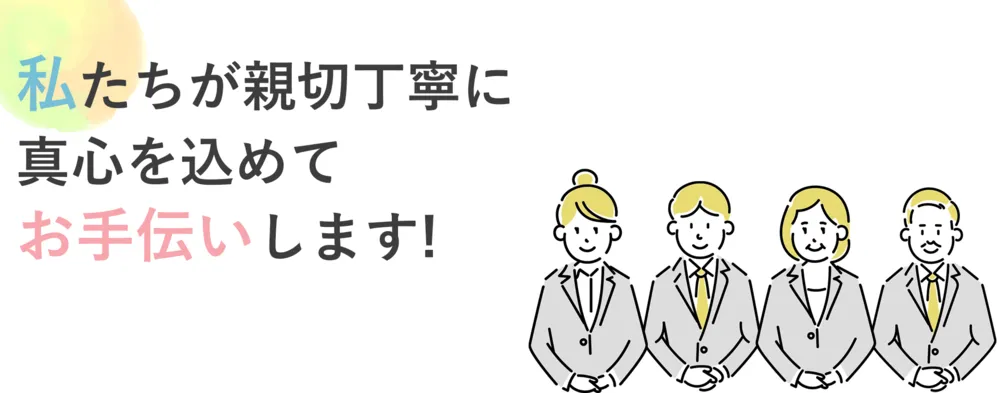
Funeral
みはしのお葬式



コンセプト

お葬式という限られた時間の中で
大切な方へ想いを伝えるために
ご遺族様とできる限りの対話を重ね
お気持ちに寄り添いながら
最期のお見送りのお手伝いをいたします。


お葬式という限られた時間の中で
大切な方へ想いを伝えるために
ご遺族様とできる限りの対話を重ね
お気持ちに寄り添いながら
最期のお見送りのお手伝いをいたします。